働きアリの法則とは?
みなさんは「働きアリの法則」をご存じでしょうか
集団の中では、よく働くアリが2割、普通に働くアリが6割、
そしてあまり働かないアリが2割に分かれるというものです
興味深いのは、この“働かない2割”を排除しても、
残った集団の中からまた新たに“働かない2割”が生まれてしまうという点です
「全員が一生懸命に働けば効率が上がるはず」と思いがちですが、実際にはそうならない
自然界の不思議であり、人間社会にも当てはまる心理現象のように感じます

働かないアリの役割
以前、YouTubeでこの法則について解説している動画を見たことがあります
その中で語られていたのは、「働かないアリは決して無駄な存在ではない」ということでした
緊急事態が発生したとき、普段働いていないアリが動き出すケースがあるそうです
「普段サボっているのに、急にそんなことできるの?」と疑問に思うかもしれません
ですが、アリの世界の“いざというとき”は高度な判断や難しい作業を伴うわけではなく、
単純に「数が必要なときに動ける要員」として機能するのだそうです
つまり、一見怠けているように見える存在も、
群れ全体のバランスを保つために必要なのだと考えると、少し見方が変わってきますよね
職場でも感じる「働きアリの法則」
人間社会にもこの法則は当てはまると言われています
例えば、私の職場にも「よく働く人」「普通に働く人」「あまり働かない人」が自然と存在しています
特に「あまり働かない人」がいると、周囲は不満を抱きがちです
「なんで私ばかり仕事をしているの?」
「同じ給料なのに不公平だ」
そんな声は、どこの職場にもあるのではないでしょうか
実際、私の職場でも頻繁にサボる人がいて、他の職員の不満の的になっています
ただ、働かないアリの法則で考えると、サボる人を排除しても、また新たなサボる人が発生します
働かない人を排除することは正解か?
では、職場から「働かない人」を完全に排除できたらどうなるのでしょう
一見すると、残った人たちで効率よく回るように思えますが、実際にはそう簡単ではありません
前述のアリのように、新たに「働かない人」が自然発生してしまうのです
人にはそれぞれ得意不得意がありますし、常に全力で働き続けることは難しいものです
むしろ「ちょっと気を抜く人」がいるからこそ、組織全体が持続可能になるのかもしれません
気にしないことが正解?
私自身も、サボる人を見て腹が立つことがあります
「なんで自分だけが頑張らなきゃいけないの」と思う瞬間も多々あります
ですが、働きアリの法則を知ってからは考え方が少し変わりました
「そういう存在はどこにでも一定数いる」
「排除しても新たに現れる」
そう理解できると、無駄にイライラせずに済む気がします
むしろ「自分はどのポジションにいるだろう?」と客観的に見つめ直すきっかけになるのです

まとめ
働きアリの法則は、自然界だけでなく私たち人間社会にも通じる不思議な現象です
職場や学校、あらゆる集団の中で「よく働く人」「普通の人」「あまり働かない人」が分かれるのは、
ある意味で自然の摂理なのかもしれません
サボる人に目を向けてイライラするよりも、「そういう人も必要なんだ」と考えるほうが、
自分の心も軽くなります
結局のところ、大切なのは「他人を変えること」ではなく「自分の捉え方を変えること」なのだと思います
常には難しくても、気づいた時に「自分の捉え方を変えていく」ことを心がけたいです
ここまで読んでくださり、ありがとうございます!!
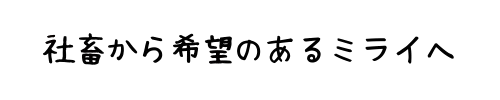
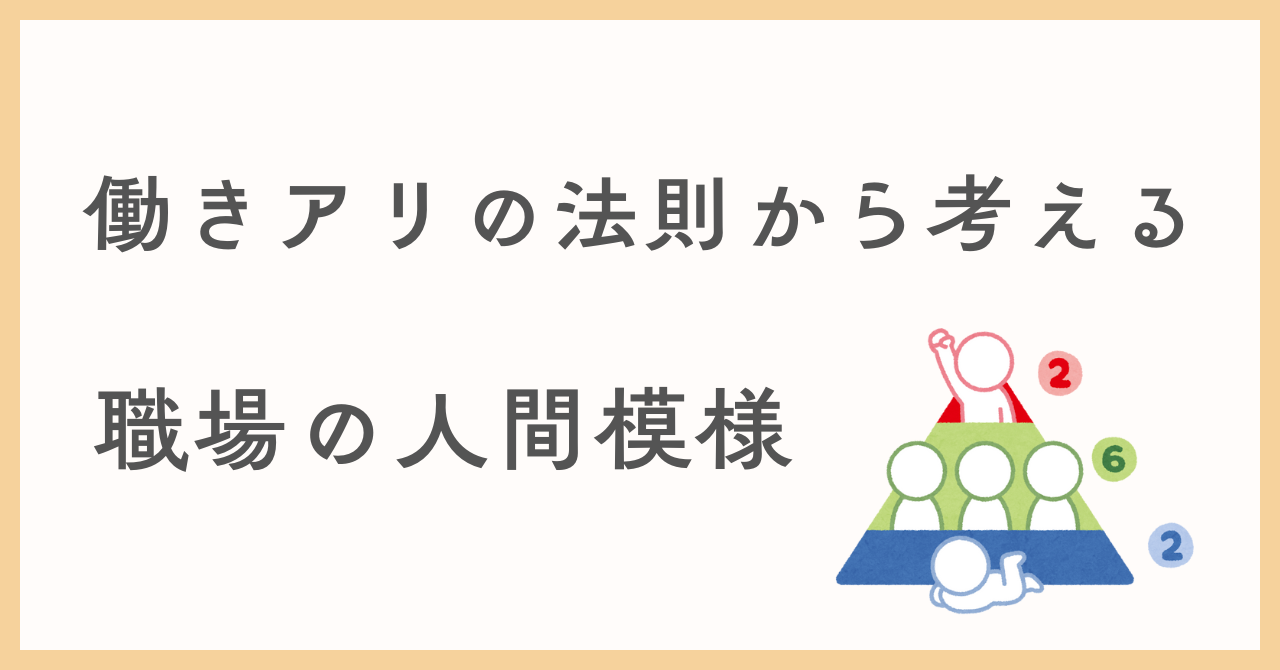

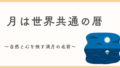
コメント