昨日の夜、散歩をしていると、暗闇にひときわ美しく月が輝いていました
満月かなと思い調べてみると、実際の満月は翌日の9月8日でした
ネイティブアメリカンは季節ごとに満月へ独自の呼び名をつけており、
9月の満月は「ハーベストムーン(収穫月)」と呼ばれます
ただし、秋分に最も近い満月が「ハーベストムーン」とされるため、必ずしも9月とは限りません
今年は10月がハーベストムーンにあたり、9月の満月は「コーンムーン」と呼ばれるそうです

海外の満月の呼び名
ネイティブアメリカンが名付けた満月の代表的な呼び名を並べると――
- 1月:ウルフムーン(Wolf Moon)…オオカミの遠吠えが響く頃
- 2月:スノームーン(Snow Moon)…雪深い冬の満月
- 3月:ワームムーン(Worm Moon)…大地が解け、虫が姿を現す季節
- 4月:ピンクムーン(Pink Moon)…野にピンクの花が咲く頃
- 5月:フラワームーン(Flower Moon)…花々が満開の季節
- 6月:ストロベリームーン(Strawberry Moon)…イチゴの収穫期
- 7月:バックムーン(Buck Moon)…雄ジカの角が生え変わる頃
- 8月:スタージョンムーン(Sturgeon Moon)…チョウザメ漁が盛んな季節
- 9月:コーンムーン(Corn Moon)…トウモロコシの収穫期
- 10月:ハンターズムーン(Hunter’s Moon)…狩猟の季節
- 11月:ビーバームーン(Beaver Moon)…ビーバーが巣を作る頃
- 12月:コールドムーン(Cold Moon)…寒さ厳しい冬の満月
自然の移ろいと生活に直結した呼び名であり、月が「暦」として機能していたことがわかります
日本の月の呼び名
一方、日本でも古来より月は人々の心に寄り添い、豊かな言葉が紡がれてきました
- 十五夜(中秋の名月):旧暦8月15日の月 お月見をする風習がある
- 十三夜:旧暦9月13日の月 十五夜と対で愛でられる
- 十六夜(いざよい):旧暦16日の月 ためらうように遅れて昇ることから
- 立待月(たちまちづき):旧暦17日の月 立って待てばすぐに昇る月
- 居待月(いまちづき):旧暦18日の月 座って待つうちに昇る月
- 寝待月(ねまちづき):旧暦19日の月 横になって待つほど遅く昇る月
- 更待月(ふけまちづき):旧暦20日の月 夜更けになってようやく現れる月
このように、日本では「月がどのように昇るか」「どんな姿を見せるか」に着目し、
情緒的で詩的な名前が付けられてきました
海外と日本の違い
- 海外:自然や農作業、狩猟など「生活の営み」と直結した実用的な呼び名
- 日本:月の昇る様子や見え方をもとに、「心情や情景」を映し出す呼び名
同じ月でも、文化によって見方や感じ方が大きく異なるのが興味深いところです
夏目漱石が「I love you」を「月がきれいです」と訳した逸話は有名ですが、
これも月を通して心を伝える日本的な感性の表れでしょう
月は世界中で人々の生活と文化を映してきた存在です
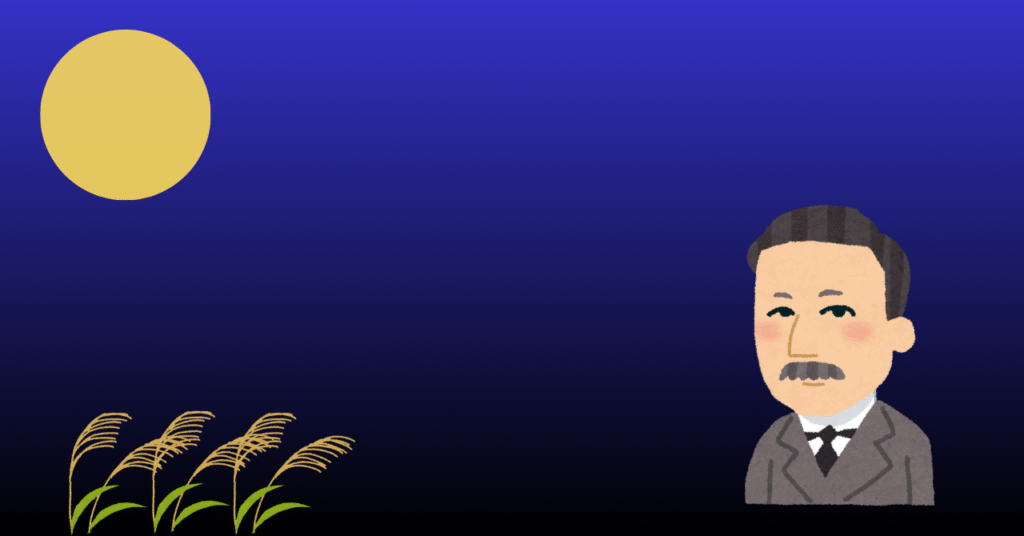
夜空を見上げれば、海外では「収穫を告げる月」、日本では「ためらいながら昇る月」
――同じ月でも多様な意味を持ちます
次の満月の夜は、そんな文化の違いにも思いを馳せながら眺めてみるのも素敵かもしれません
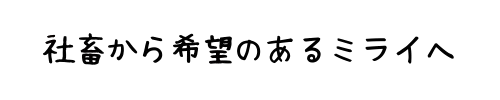
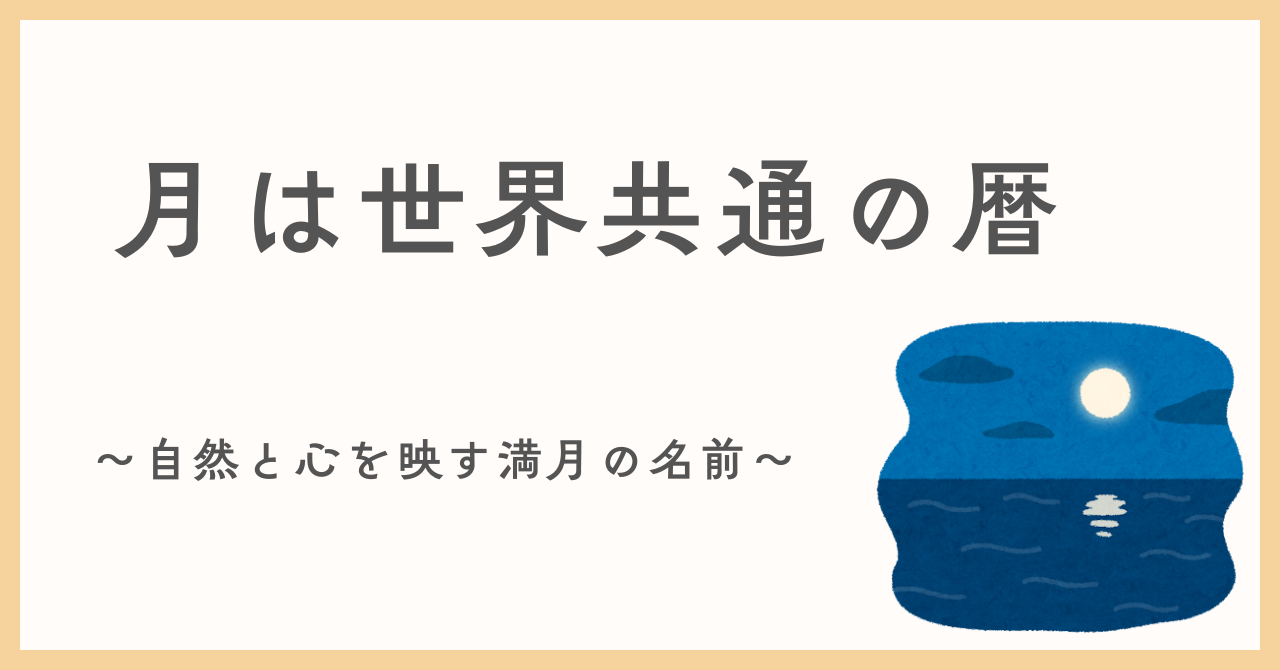
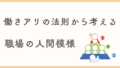
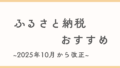
コメント