教師期待効果とは?
「教師期待効果」という言葉をご存じでしょうか。
これは教師が生徒に「あなたはきっとできる」と期待をかけることで、
生徒がその期待に応えようと努力し、成績や意欲が向上する現象のことです。
心理学では ピグマリオン効果 と呼ばれています。
この効果は、1968年にアメリカの心理学者ローゼンタールが行った有名な実験で示されました。
ある学校で無作為に選ばれた子どもたちを「この子たちは将来伸びる」と教師に伝えたところ、
数か月後に実際にその子どもたちの成績が上がったのです。
つまり、教師の「期待」が現実を動かすことを証明したのです。
一方で、その逆も存在します。
否定的な期待をかけられると、パフォーマンスが下がってしまう現象です。
これは ゴーレム効果 と呼ばれます。
「どうせできない」という目で見られ続けると、本当にできなくなってしまう
――まさに「自己成就予言」の負の側面です。
子どもの頃に感じたゴーレム効果
私自身、小学生の頃に「嫌いな先生」がいました。
何をしても否定され、「どうせお前はできない」と言われているような感覚でした。
そのたびに、心が縮こまっていったのを覚えています。
子どもにとって学校は生活の大半を占め、接する大人といえば家族と先生くらいです。
だからこそ先生の言葉は絶対的な力を持ちます。
「先生がそう言うなら自分はそうなんだ」と思い込んでしまうのです。
結果として自己肯定感は大きく下がり、挑戦する意欲まで失われてしまいました。
大人になってから振り返ると「ただの一教師の言葉」と切り離せる部分もありますが、
子どもの頃に植え付けられた感覚は簡単には消えません。
私にとっては、それがまさにゴーレム効果の体験だったのだと思います。
教師という職業の難しさ
もちろん、教師も一人の人間です。
全ての生徒に同じように接することは簡単ではありません。
可愛がりたい子もいれば、手がかかる子、特に目立たない子もいる。
知らず知らずのうちに態度や言葉に差が出てしまうのは仕方ないのかもしれません。
しかし、その「小さな差」が子どもにとっては人生を左右するほど大きな意味を持ちます。
期待をかけすぎればプレッシャーになり、期待されなければやる気を失います。
ピグマリオン効果とゴーレム効果の間で、
ちょうどいい塩梅を見つけるのは本当に難しいことだと感じます。
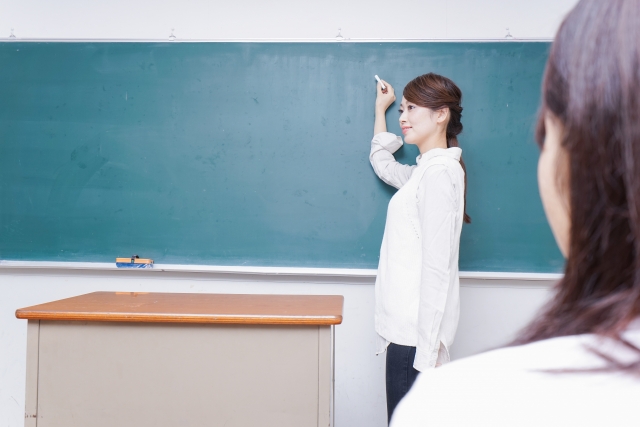
教師だけではない「期待の力」
この効果は、教師だけに当てはまるものではありません。
職場の上司が部下に対して抱く期待、親が子どもにかける言葉、友人やパートナーとの関わり方
――すべての人間関係に影響します。
「君ならできる」と言われて勇気づけられた経験は誰しもあるのではないでしょうか。
反対に「お前には無理」と言われて自信をなくした経験もあるかもしれません。
期待や評価は、それほど大きな力を持っています。
言葉が人を育てる
子どもにとって先生は、将来どんな大人になるかの方向性を決める存在です。
だからこそ、期待や評価の言葉をどう使うかには、細心の注意が必要だと思います。
私自身、ゴーレム効果を強く感じたからこそ、
「人に期待を伝えるときはポジティブに」という意識を持つようになりました。
子どもであれ、大人であれ、「できるかもしれない」という期待が、
人を前に進ませるのだと信じています。
先生だけでなく、親も上司も、友人も――言葉一つで人を押し上げることも、押しつぶすこともできる。
だからこそ、私たち一人ひとりがその力を意識しながら使っていけたらと思います。
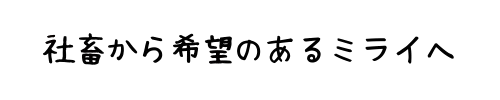
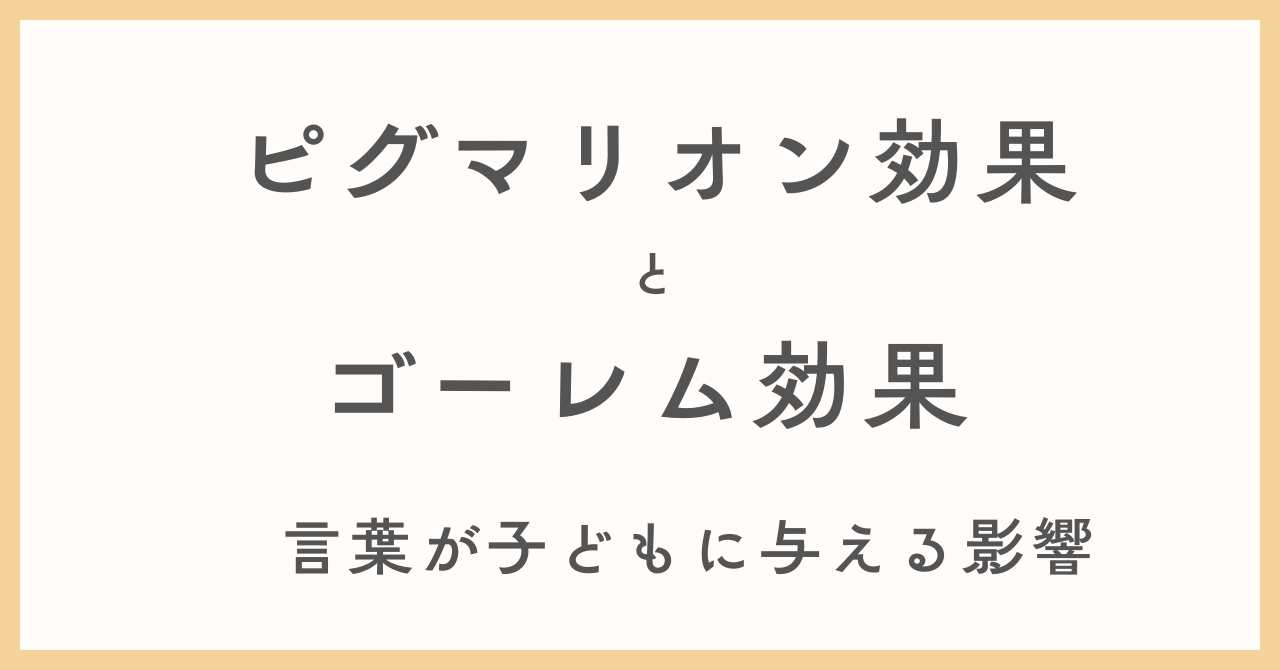
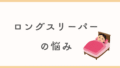
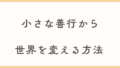
コメント